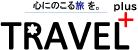日本ではいろんな種類のお茶づけの素があって、ささっとご飯を済ませたいときやあまり食欲がない時などに食べられています。

マレーシア人にお茶漬けは受け入れられる?
マレーシア料理ではお茶漬けの文化は一般的ではありません。
日本のお茶漬けを紹介しても「ご飯にお茶?美味しいわけがないよ」という反応が普通です。
実は、お寿司、ラーメン、照り焼き、カツなど日本食が大好きなマレーシア人でも、一部の和食は「味がしない」と感じるようです。
例えば、おでんにはべったりと唐辛子ソースをつけてやっと「美味しい!味がする!」と言い、お出汁の効いた鍋料理は「味がついていない?もっと塩分ちょうだい」と感じることもあるようで、お茶漬けもその部類に入るかもしれません。
日本のお出汁の文化は素晴らしいのになぁと少し残念に思った事があります。
マレーシアで日本のお茶漬けを発見!
ところで、マレーシアで人気を博しているファミリーマートですが、店中に充満するむせかえるほどのトムヤムクンの匂いに、その人気の秘密があります。
正体はこれです。

トムヤムクン味のおでんです。
これがマレーシア人に大人気なのですが、私は未だこの匂いを受け入れることができず、食べたことはありません。
そして気がつきました、さすがファミリーマート!

メニューをよくみると、なんと日本のお茶づけが!!
鮭茶漬けです。
日本のお出汁についても説明がしてあり、日本のお出汁文化を広めようとしているのが伝わってきました。
お出汁のきいたうどんもとっても嬉しいので、このままメニューから消えてしまわないといいなと願っています。
お茶漬けが人気メニューかどうかは不明ですが。
マレーシアにもお茶づけがあった!
ところで、マレーシアンチャイニーズの祖先は中国大陸からマレーシアに移り住む際、広東、四川、客家、北京、上海などからそれぞれの食文化を持ち込みました。
これはマレーシアの食文化がバラエティーに富んでいる理由の一つです。
日本では聞いたこともない中華料理がたくさんあり、比較的日本人の舌に合ったものが多くあります。
そしてついにある時、客家のレストランでお茶漬けらしきものを発見しました。

レイチャの特徴は
これはレイチャという料理で、肉を一切使用していないのでベジタリアンでも食べられます。
ご飯にたくさんの野菜をのせて、スープをかけていただきます。
今回のレイチャは、キャベツ、ロングビーン、海藻、赤キャベツ、にんじん、きゅうり、大根の漬物、ピーナッツが小鉢に入っています。
具材をご飯の上に全部のせ、急須に入ったスープをかけたものがこちらです。

スープの緑の濃さに驚かれるかもしれません。
これは緑茶…ではなく、なんとミントやバジルで作ったハーブスープなんです。
これがレイチャの1番の特徴です。
イメージとしては、塩分のきいた青汁みたいな感じです。
ミントが強めなので、好き嫌いは別れるかもしれませんが、グリーンスムージーを飲み慣れた人なら、抵抗なくいけるんじゃないかと思います。食べてみると、スープはとてもあっさりしていて、ピーナッツのサグサグした歯応えと大根の漬物がものすごいいいアクセントになっています。
後味はさっぱりしていて、脂っこいものが多い中華料理の中で、体にいいもの食べた!と思える料理です。
最後に
余談ですが、お店によってスープの味が全然違います。
ただ緑くさいだけで味がしないスープだったこともあるので、当たり外れがある、と思ってチャレンジしてみてください。
食い倒れツアーの合間に、胃を休めるにはレイチャすごく良いと思います。
見つけたらぜひお試しください。